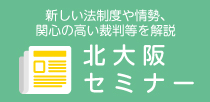「国は、国民の生命健康にどう向き合うべきか」を問う 8年半に渡る闘いの末に得たもの~泉南アスベスト国賠訴訟の闘い~
Ⅰ 泉南アスベスト国賠訴訟の闘いを振り返って
今年の10月で泉南アスベスト国賠訴訟最高裁判決から3年になる。私は、最高裁判決の直後に、「社会的な力も組織力もない泉南地域の『無告の民』が立ち上がり国に闘いを挑み、8年半の闘いの末に最高裁で国の責任を認めさせた。『民衆の闘い』の歴史的な勝利である」、と高揚した気分で書いた(労旬1837号「大阪・泉南アスベスト国賠訴訟最高裁判決の意義と課題」)。
泉南アスベスト国賠訴訟の闘いとはいったい何だったのか。本稿の依頼を受けて、今、改めて振り返って考えてみた。
泉南アスベスト国賠訴訟のルポルタージュである「国家と石綿」(永尾俊彦著・現代書館)は、泉南アスベスト被害と最高裁判決の位置付けについて次のようにいう。
「(国は)『知っていた、できた、でもやらなかった』という泉南石綿国賠訴訟のスローガンは、泉南の石綿被害だけでなく、さかのぼれば南米移民や満蒙開拓、アジア太平洋戦争、戦後の高度経済成長期の水俣病などの公害から2011年の福島原発事故にも通じる近代日本の国家的『棄民政策』をわかりやすく言い換えた言葉」である。「新しい『棄民政策』の被害者が全国各地で生まれている。いつまでたっても同じことの繰り返しで絶望的な気分になる」(同書349頁)。
泉南アスベスト被害を、国家の棄民政策の歴史のなかに位置付けるのは正鵠を射ている。泉南地域の石綿工場の労働者、住民らは、国の高度経済成長の「捨て石」、犠牲にされたのであり、その被害は長きにわたって黙殺されてきたのである。2006年、歴史から黙殺されていた人々が立ち上がり、国の責任を問うたのが、泉南アスベスト国賠訴訟であったといえよう。
永尾氏は、泉南最高裁判決の意義について「泉南アスベスト訴訟を勝たせる会」の事務局長であった伊藤泰司氏の「人の命の重みを重くする判決」という言葉を引用し、「このような判例の積み重ねによって1歩1歩国策の誤りが正され、人の命は重くなっていく。その重要な一歩に泉南石綿国賠訴訟の勝利も位置付けられるだろう」(同書349頁)という。
弁護団の一員として、「人の命の重みを重くする判決」「1歩1歩国策の誤りを正す判決」という言葉はとりわけ胸に響く。アスベストによって奪われた生命健康は決して戻ることはない。国賠訴訟で勝利して賠償金を取得し、厚労大臣の謝罪を勝ち取ってもそうである。ましてや8年半の長い闘いのなかで、16名の被害者原告が解決を見ることなく、国の謝罪を聞くこともなく、無念のうちにこの世を去ったのだ。被害者の無念さや犠牲を無にしないために、国は、泉南最高裁判決を真摯に受け止めて、アスベスト政策、その根底にある産業経済発展を優先させ国民の生命健康を蔑ろにする姿勢・政策を改めてほしいと強く願わざるを得ないのである。
しかし、最近の各地の原発の再稼働や沖縄の辺野古沖埋立て強行などを目の当たりにすると、残念ながら、この国の棄民政策はいささかも変わっていないと感じる。福島原発事故の甚大な被害を経てもなお、住民らの生命・健康・住環境は、国家のエネルギー政策や電力産業保護の下位に置かれている。沖縄住民の生命・健康・平穏な生活は、日米安保条約の前に一顧だにされていないと思える。
また、最高裁は、辺野古埋立て承認取消処分の違法確認訴訟で沖縄県知事を敗訴させ、大阪高裁は、関西電力高浜原発運転を差し止めた大津地裁仮処分決定を取消した。平成18年のアスベスト全面禁止後に提訴し、過去の国策の誤りと規制の不十分さ追及した泉南アスベスト国賠訴訟と対比すると、司法も、基地や原発問題など「現在進行形」の国策の根幹にかかわることに異を唱えることに消極的である。
さらに、労働分野では、安倍内閣の「働き方改革」は生産性向上を第1の目標に掲げ、過労死ラインを超える「100時間未満」を労働時間の上限として設定しようとしている。しかし、100時間未満での労災認定されたケースは、2015年度で54件(56%)に上っており、政府の方針は、過労死ラインまで働かせることにいわば「お墨付き」を与えるものであって、ここでも、生命健康よりも企業の利益保護を優先させている。
それゆえにこそ、これからも、労働、公害、環境などあらゆる領域で、棄民政策の被害者が声を上げて被害を告発し、被害救済と予防に向けた幅広い連帯と国民的な運動を絶え間なく展開することが大切になるのだろう。そして、司法の分野でも、厳しい情勢のなかでも「命の重みを重くする判決」を積み重ねることで「1歩1歩国策の誤りを正す」ことが求められるといえよう。
そこで、泉南アスベスト訴訟の闘いの経過(運動と裁判)を若干のエピソードを交えながら振り返った後、何故勝てたのか、闘いの到達点を述べてみたい。じん肺訴訟、水俣訴訟等の公害訴訟、基地訴訟など多くの先進的な闘いと教訓があるなかで、泉南アスベストの闘いがどれだけのものを積み上げられたかは心許ないが、現在、そして、これからの国民の生命健康を護る闘いの参考の一つとしていただけければ幸いである(なお、泉南アスベスト訴訟の経過と闘いは、村松昭夫「大阪泉南アスベストの闘い」、伊藤明子「大阪・泉南アスベスト国賠訴訟の経緯とこれからの課題」労旬1837号に詳しい)。
Ⅱ 闘いの経過
1 何故、闘いに立ち上がったか
アスベスト被害のうち石綿肺は、古くから知られていたが、一部の労働者の職業病であると捉えられていた。それが平成17年6月のクボタ神崎川工場の従業員、周辺住民がアスベストを原因とする悪性中皮腫などで死亡したことが公表された(いわゆる「クボタショック」)。そして、輸入された1000万トン以上のアスベストの約8~9割が石綿建材・吹き付け材に使われ、建物解体により石綿粉じんの飛散ばく露の危険性があり、自分達にも無関係な問題ではないと一般市民が感じたことで、アスベスト問題は大きく「社会問題化」した。国は、アスベスト問題に関する政府の過去の対応を検証したが、省庁間の連絡が不十分であったとするのみで、責任を認めなかった。平成18年2月成立の石綿救済法も国に責任があることを前提としたものではなく、内容も不十分であった。当時、石綿救済法の環境省の担当審議官は、石綿関連のシンポにおいて、今後アスベスト問題で国賠訴訟が提訴されても原告が勝つ可能性は限りなく0%に近いと発言した。
クボタショック直後、弁護団と民医連の医師団、市民の会のメンバーは、泉南地域で医療法律相談会を開き、隠れていた被害を掘り起こした。平成18年5月、石綿工場の元労働者、家族、周辺住民らを原告団として組織し、1陣訴訟を提訴した。戦前から石綿工場が集中立地していた「アスベスト被害の原点」の地で国の責任を明確にし、完全な補償の実現と将来の被害防止が目的であった。原告団は、被害者数で1陣訴訟26名、2陣訴訟33名となった。
2 画期的な1陣地裁判決
平成22年5月19日大阪地裁で石綿による健康被害について初めて国の責任を認める判決を勝ち取った。昭和46年以降も含め、昭和35年以降の国の全部責任を認める画期的な判断であった。この判決は、「いのちを大切にする政治」を標榜する民主党政権で初めての大型国賠訴訟判決であり、当時の長妻厚労大臣、小沢環境大臣はいったん控訴断念を表明した。しかし、鳩山総理大臣が仙谷国家戦略担当大臣に最終判断を一任し、国は6月1日に控訴し、鳩山内閣は、6月4日に普天間問題で総辞職した。もっとも、国は、「一応控訴はするが、控訴審で和解もあり得る」とコメントした。
3 奈落の底に落ちた1陣高裁逆転敗訴判決
原告らの和解勧告の上申を受けて、裁判所から国側に打診がなされたが、国は和解のテーブルに着くことを拒否した。三浦裁判長は、「全力で判決を書く」と宣言し、近隣曝露の位置・距離関係を事実上検証するため、現地に赴き、症状が進行するなどした5人の原告本人尋問を実施した上、結審した。原告団・弁護団内では、地裁判決で否定された近隣曝露被害を含めて勝訴できるのではないかとの期待が一挙に高まった。ところが、平成23年8月25日、フタをあけてみると、近隣どころか労働者の被害についても国の責任を全て否定する全面敗訴判決であった。法廷で芝原団長が不当判決と声を上げたが、私は現実のこととは思えず、呆然とするばかりであった。原告は法廷で泣き崩れ、動けなかった。マスコミは「弁護団が掲げる『不当判決』をこれほど実感を持って眺めたことはない」(朝日新聞)「経済優先の暴挙」(毎日新聞)と報じた。
正直いうと、上告受理率が5%、原判決破棄率が2.5%であると聞いたことがあったので判決直後は暗澹たる気分であった。私が励まされたのは、判決後の東京行動で団体の支援要請周りをしているときのある原告の言葉だ。「判決を聞いて、(敗訴することを)先生らはわからなかったのかと思い、(弁護士さんも悪いのではないかと)疑った。でも先生らが、負けてもこうやって一生懸命やっているのを見て、間違っていたと思う。上告して頑張る」と。
原告らは、全員上告・上告受理申立した。印紙代が570万円かかるので、併せて訴訟救助申立を行ったところ、同じ大阪高裁第14民事部において速やかに全額の訴訟救助決定がなされた。全国1035名の弁護士が上告審の代理人就任を承諾してくれた。判決直後から弁護団は不当判決を法的にも事実認定の面でも徹底的に批判しつくす作業を行い、事実誤認と法的評価の誤りを明らかにした(『問われる正義―大阪・泉南アスベスト国賠訴訟の焦点』かもがわブックレット・参照)。公害弁連、じん肺弁連など全国の弁護士、学者、元最高裁裁判官の意見を聞き、わかりやすい上告受理申立書を作成した。その後も、法律学者と研究会懇談会を行った。多くの学者が1陣高裁批判の論文を雑誌に掲載し、その都度、上告受理申立補充書として提出した。2年半で合計17回弁護団・原告団が上京して最高裁要請行動を行い合計14回の上告受理申立理由書の補充書を提出した。
4 反転攻勢の2陣地裁
最高裁での逆転勝利に向けて、係属中の2陣訴訟が大きな役割を果たした。
弁護団は「2陣訴訟の地裁、高裁判決で必ず勝利判決を勝ち取り、最高裁に1陣高裁判決を取るのか、2陣高裁判決を取るのかを迫ろう」という戦略を立てた。それからが、負ければおしまいという崖っぷちの闘いの連続であった。
まずは、結審間近であった2陣地裁である。原告からも同じ高裁管内で地裁が、直前の高裁判決に反する判決を出すのかという不安の声が出された。結審期日では、「炎の弁論」と傍聴席から感想が出るほどの1陣高裁判決の徹底した批判と国の責任を明確にする弁論を行った。そして、平成24年3月28日、2陣地裁判決は、昭和35年から同46年までの国の責任を肯定した。不当判決からわずか7カ月後の勝訴判決の意味は大きかった。反転攻勢の足がかりができた。
5 事実審の最終決戦の2陣高裁
2陣高裁では1陣高裁と同じ誤りを繰り返すことは許されない。控訴審では第1回期日前に合議が行われ、一定の方向性が出される。そこで、第1回期日の1ヶ月前に国の控訴理由書に対する反論書を提出し、「事実審の最終決戦」と位置づけて国側の専門家証人を徹底して弾劾し、国の主張立証を反論し尽くした。
平成25年12月25日、2陣高裁判決の言い渡しは生涯忘れられない。判決の要旨の読み上げが進むなかで、「昭和33年から」「昭和47年以降も」「国の責任は2分の1」と、国の責任が長期間かつ重く認められたことがわかった。1陣高裁判決後の苦しかった2年半のことが脳裏をよぎり法廷で初めて落涙した。2陣高裁判決は、1陣高裁を厳しく批判するものであり、事実認定でも法律論でも弁護団が勝ち取った判決のなかで最も優れたものであった。
6 最高裁判決
平成26年6月、最高裁の書記官から「1陣、2陣訴訟の弁論を開くので、期日を調整したい」との電話があった。私が「1陣の弁論でしょう」と何度問い直しても「いや、1陣、2陣双方の弁論を開く」という。しかも、送られてきた上告受理通知書では、1陣・2陣訴訟とも同一争点で上告が受理され弁論が開かれるという前代未聞の内容であった。弁論が開かれるということは原判決が見直されるということであり、事前に結論はわかるのであるが、これでは判決を聞くまで結果がわかない。弁護団は、基本的には勝訴できるであろうが、2陣高裁判決の昭和47年以降の違法の判断の維持に危惧を持ち、時期で区別することなく原告全員の救済を求める弁論を行った。
平成26年10月9日、最高裁は、昭和33年以降から昭和46年までの国の責任を認めたが、昭和47年以降の責任を否定した。法廷で判決の言い渡しを聞きながら「勝つた」と大いに安堵したが、被害者救済が分断されたことには、正直落胆した。法廷の外から、「勝訴」の旗出しに、どっとわく支援者らの歓声が聞こえるなか、昭和47年以降の弁論を担当した弁護士は悔し涙を流していた。
7 最終解決へ
平成26年10月18日、原告団総会で私は次のようにあいさつした。
「救済されなかった原告の無念は、原告団・弁護団みんなの無念であり、その悔し涙は、みんなの悔し涙です・・。原告全員が、裁判中に亡くなった被害者も含めて、石綿工場の内外、就労の時期を問わず、法廷内外で、自らの被害を訴えることで、泉南地域の石綿被害が、地域ぐるみで長期かつ広範なものであることを明らかにし、被害救済の大きな世論をつくり、最高裁判決を勝ち取ったのです。原告全員で勝ち取った最高裁判決であることをここでもう一度確認したうえで、これまでどおり、団結して、全面解決に向かいましょう。」
平成26年12月26日、1陣訴訟差戻し審で①厚労大臣の謝罪、②国は確定した2陣訴訟と同じ基準で賠償金を支払う、③未提訴者についても訴訟上の和解を行うなどの和解が成立し、平成27年1月18日、塩崎厚労大臣が泉南を訪れて原告らに謝罪した。
Ⅲ 何故、勝てたのか。
1 永尾氏は、次のようにいう。
「何故泉南国賠訴訟は勝てたか。その答えを探していて『群像の勝利』という言葉が脳裏に浮かんだ」「泉南の原告、弁護士、支援者らも勝つまでも闘い続けた。その勝利にも傑出したリーダーがいたわけではない。それぞれがそれぞれの役割を十二分に果たした協働が勝利につながった」「原告は、石綿の病を得ることはどういうことか、普通に息ができない苦しさはどのようなものか・・自らの言葉で懸命に語った」「弁護士は、このような原告の姿に感応し、この原告を勝たせたいと資料を渉猟し証拠を集積し、膨大な訴状、準備書面、意見を作成し、あえて心を鬼にして、いまわの際で苦しむ原告の姿をDVDに治め、裁判所で上映した」(353頁)。
2 弁護団は、公害・環境・労働弁護士、元特捜検事、若手と多彩なメンバーで構成されていた。大学研究者らと共同して国内外の膨大な医学的・工学的知見の収集、海外文献を翻訳し、被害者の自宅に通い詰めて被害を聴き取り、陳述書を作成し、原告本人尋問の準備をした。準備書面や弁論、尋問事項には互いに徹底的に修正意見を言い合い、要所では裁判所をどうみるかなど徹底した議論をした。それぞれの弁護士が自分の持ち場で役割を果たし、全体として集団的討議でさらに高めることによって、国の主張立証を論破し、裁判所を説得することができたように思う。加えて、弁護団を超えて、学者や元裁判官、他の弁護団などあらゆるところに教えを請うたことも大いに役立った。
また、運動面では、原告、弁護団、支援団体が法廷の度に宣伝活動、公正判決署名を行った。合計5回の判決後の東京行動での厚労省前、官邸前宣伝行動、院内集会、超党派の国会議員の解決賛同アピール集め、国会通信を議員会館に全戸配布した。与党、野党を問わず徹底したロビー活動を展開したことが厚生労働省に最終和解決断をさせる大きな力となった。運動方針をめぐり弁護団と支援者の間での様々な議論があったが(詳細は「国家と石綿」参照)、最後は、原告団・弁護団・支援者の一致団結を保つことができた(永尾氏は「原告・弁護士・支援者が他の人の主張に耳を傾け、自らをふり返る姿勢をもっていたからではないか」という)。
さらに、世論が好意的であったことも勝因の一つである。
泉南訴訟の原告が、労働者にとどまらず、周辺住民や家族も原告に加わったことは、アスベスト被害が住民も含めた幅広い被害であることをアピールし、「社会問題化」するうえで大きな意味があった。弁護団は、提訴や判決や集会などの行事ごとにマスコミ向けのレクチャーを行い、報道してもらった。それゆえ、1陣地裁で初めて国の責任が認められたときマスコミの多くは好意的であり、1陣高裁で逆転敗訴したときマスコミの大半は判決に批判的であった。最高裁は政治的で世論の動向に敏感であり、マスコミ世論を味方につけることは極めて重要である。
Ⅳ アスベスト被害救済の闘いの到達点と課題
泉南アスベスト訴訟最高裁判決は、労働安全行政の分野に関するものである。しかし、高裁レベルで、国民の生命健康を第一とするのか、産業発展との利益考量するのか、判断が正反対にわかれたこともあり、「国は、国民の生命健康にどう向き合うべきか」という行政のあり方の根本問題に関する判断が、最高裁に求められたものといえる。国側の訟務検事も、論文で「規制権限の不行使の問題は、被害回復の側面で国の後見的役割を重視して被害者救済に力点を置くと、事前規制型社会への回帰と大きな政府を求める方向につながりやすい。それが、現時点における国民意識や財政状況から妥当なのか否かといった大きな問題が背景にある」と裁判所を牽制した。最高裁が、憲法と法令に則り、生命・健康こそが至高の価値であり、国は、国民の生命・健康被害を防止するために「迅速」かつ「適時・適切な」規制権限を行使する義務があることを改めて明確に判断したこと、被害者救済の立場に立ったことに本最高裁判決の最大の意義がある。
もっとも、最高裁は、近隣・家族被害は審理の対象とせず、昭和47年以降の防じんマスクの使用義務づけ違反の違法を否定した。これは、石綿工場では、局所排気装置の設置が第一次的な方策であり、防じんマスクは「補助的手段としての位置づけ」だからである。泉南最高裁判決は、国に対して、それぞれの石綿粉じん作業の特徴に応じた最も効果的な粉じん対策を「適時かつ適切に」義務づけることを求めているものといえる。
そして、建設アスベスト訴訟では、東京地裁に続く、泉南最高裁判決後の福岡、大阪、京都、北海道の各地裁判決は、 建築現場では、局所排気装置の設置が困難であり、防じんマスクが「重要で効果的な粉じん対策」であったとして、その使用義務づけ違反の国の責任を認めている。大量輸入と大量使用が続いた時期における国の責任を認める司法判断の流れは固まった。
これから建設アスベスト訴訟で全国の高裁での判決が続く。焦点は、建材メーカーの責任、一人親方に対する国の責任に移っている。建設アスベスト被害の早期全面解決のためにも「人の命の重みを重くする判決」を一つ一つ積み上げなければならない。