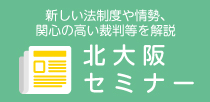羽衣学園事件 最高裁で大阪高裁判決を覆す不当判決
第1 はじめに
2024年10月31日、最高裁第一小法廷(岡正晶裁判長)は、学校法人羽衣学園事件において、不当にも地位確認請求を認めた大阪高裁判決(2023年1月18日)を破棄し、原告が就いていた生活福祉コースの専任講師の職(「本件講師職」)が大学教員等の任期に関する法律(「任期法」)4条1項1号所定の「多様な人材確保が特に求められる教育研究組織の職」に該当すると判断して、5年無期転換を否定しました。なお、その余の部分についてさらに審理を尽くすように大阪高裁に差し戻されました。
第2 本件の概要と争点
そもそも労働契約法18条は、有期雇用労働者の雇用の安定を図る趣旨で、有期雇用契約が通算5年を超えて更新されている場合には無期雇用契約に転換することを定めています。これに対して、任期法は、大学教員の流動性を高めることで教育研究の活性化を図る目的で、①多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき(流動型)、②助教の職に就けるとき(助教型)、③特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき(有期プロジェクト型)の3類型の場合に任期を定めることができるとし(任期法4条1項)、これらに該当する場合には、無期雇用への転換を5年ではなく10年とする特例を設けています(任期法7条1項。「10年特例」)。
原告は、学校法人羽衣学園が運営する羽衣国際大学人間生活学部人間生活学科生活福祉コースで2013年4月から介護福祉士を養成するため専任講師として有期契約で雇用され、その後2回更新を行い通算6年となったことから、2018年11月に無期転換を申し入れました。これに対して、大学側は「10年特例」により、無期転換は認められないものと主張し、2019年3月末で原告を雇い止めしました。
第3 本件の経過
原告は、恣意的な「10年特例」の適用が不当であるとして、2019年5月31日に大阪地裁に提訴しましたが、大阪地裁第5民事部(中山誠一裁判長)は、2022年1月31日に、原告敗訴判決を言い渡しました。
原告が控訴したところ、2023年1月18日、大阪高裁第7民事部(冨田一彦裁判長)は、「10年特例」は労働契約法18条の例外であることから、これを限定的に解釈するべきだとして、介護福祉士養成課程を担う原告が就いていた職は任期法4条1項1号には該当しないとして、「10年特例」の適用を否定して、無期転換を認めて、原告の地位確認及び賃金請求を認容する逆転勝訴判決を言い渡しました。
第4 最高裁判決の内容と不当性
ところが、最高裁は2024年10月3日に弁論を開き、同月31日に大阪高裁判決を破棄し、その余の点について更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻す判決を言い渡しました。
最高裁は、大阪高裁判決の立場とは異なり、任期制を採用するか否かや、任期制を採用する場合の具体的な内容及び運用につき、「各大学等の実情を踏まえた判断を尊重する」べきだとして、「任期法4条1項1号の教育研究組織の職の意義について殊更厳格に解するのは相当ではな」く、介護福祉士養成においても実務経験を生かした実践的な教育研究が行われていたことから、本件講師職は任期法4条1項1号に該当すると判断しました。
しかし、最高裁判決の立場ではいかなる場合に任期法4条1項1号に該当するのか基準は明確ではなく、結局のところ大学側が恣意的に「10年特例」を運用する余地が認められてしまいます。本件でも、原告の採用時や2度にわたる契約更新時には、「10年特例」が適用されるといった説明は一切なされていなかったにもかかわらず、原告が5年無期転換を申し入れた後になって、大学側は不意打ち的に「10年特例」を主張し始めました。このような恣意的な運用が許されてしまうと、いつの時点で無期転換権を行使できるのか不明瞭となり、原告のような有期雇用の大学教員の地位は非常に不安定なものとなってしまいます。
第5 今後の闘い
今後は再び大阪高裁に闘いの場を移します。最高裁は差戻審の対象を明確に判示しませんでした。主な争点は雇止めの有効性となると予想されますが、恣意的な「10年特例」の適用を阻止するために原告・弁護団・支援者とともに検討を重ねていきたいと考えていますので、今後もご支援のほどお願いいたします。
(弁護団は鎌田幸夫弁護士、中西基弁護士、西川)